■
 【送料無料】教え上手 |
51−52頁、「すぐれた教師ならどうするか。青や赤でなく黄色に着目するはずです。なぜなら信号の色のなかで、いちばん意味があいまいで、対応もむずかしいのが黄色だからです。「黄色は注意」というが、具体的に、どう注意すればいいのか。注意しながらわたってもいいのか。それとも、自重して渡るべきでないのか。注意の意味が判然としません。黄色は赤と青の中間にある暫定的な指示であり、それだけにどう対応していいものやら、歩行者や運転手を迷わせる色なのです。大人が迷うぐらいですから、小学生はもっと困るでしょう」。
103頁、「知識や言葉を実感的に体得するためには、行動や経験という氷山に支えられている必要があります。知識や言葉は経験という氷山の一角であってはじめて、人生や生活のなかに生かせるものなのです」。
146頁、「事前の予想どおりに進んだということは、すなわち、予想どおりにしか進むなかったということであり、それは教わる人たちの発言が少なく、交流にも乏しい、ダイナミズムに欠けた授業であることの証しだからです」。
170頁、「より具体的にいえば、形容詞を思い切って省くことです。主語と述語だけを使って、文章の骨組みをスッキリさせるのが書く技術の基本であり、形容詞はなるべく使わないようにすることが肝心なのです」。
184頁、「いつの時代も子どもや若手はそれよりも上の世代から、「最近の若い者は・・・」といわれます。上の世代から見たときに、彼らの言動が理解できないからです。理解できないものに対しては、批判的な意見の方がいいやすくなってしまいます。しかし、だからこそ「よい先入観」が必要なのです。だれにも絶対よいところがある。だから何としてでも、それを探し出してやる・・・そういう庁積極的な態度で人に接し、見出した長所をさらに伸ばしてやること。人材育成の最大のポイントはそこにあるのです」。
189頁、「人を見る目は減点主義であってはならないのです。人間は不足と欠陥の動物ですから、あら探しをすれば、いくらでも欠点が見つかります。しかし、そんな刑事のような目でばかり見ていては相手との信頼関係は築けません。教える人が持つべきは「裁く目」ではなく「育てる目」であるべきなのです。だから、悪いところがあっても極力それを見ない。一方で、いいところには大いに着目する。そんなふうに視点のスイッチを切り替えていれば、しだいに悪いところが目に入らなくなり、目に入っても忘れられるようになります」。
205頁、「その、ほめると叱るを反対の行為だと思っている人が少なくありません。しかし、このふたつはいずれも人に対する愛情の違うあらわれ方です。「可愛くば五つ教えて、三つほめ、ふたつ叱ってよき人とせよ(二宮尊徳)」。
208頁、「このとき注意しなくてはいけないのは、そのルールや基準が不確かであったり、そのときどきで変わってしまうことです。同じことをしても機嫌のいいときには叱らないが、虫のいどころが悪いとカミナリが落ちる。昨日は激しく叱ったのに、今日は知らん顔をしている。こういう恣意的な叱り方をしていると、子どもに限らず教わる人はルールを守るよりも教える側の人の顔色をうかがうことに熱心になってしまいます。叱る基準は一貫していることが大事なのです」。
209−211頁、叱るときの5つのポイント。「強く、短く叱る」「相手の身になって叱る」「目を見て叱る」「他人と比較して叱らない」「いまのことを叱る」。
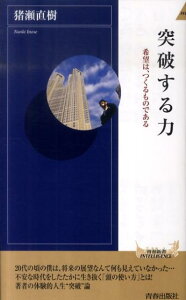 【送料無料】突破する力 |
100頁、「具体的には、キーフレーズを書き、相手に指し示しながら話をします。紙にはキーワードではなくキーフレーズを書きます。キーワードは「何をどうする」の「何」に当たる部分です。会議やプレゼンの目的は、「どうする」の部分を決めること。自分の主張もそこに集約されるのだから、述語を入れて立場を明確にしなければいけませsん。たとえば「○○プロジェクトについて」ではダメ。「○○プロジェクトは中止すべき」というフレーズにして、初めてビジュアルの効果が発揮されます」。
114頁、「大切なのは、「何のためにこの規則があるのか」という目的を見極めて柔軟に対応すること。「決まりだから」と思考停止に陥るのではなく、「なぜこの規則が作られたのか」という理由を考えてみる。そうすれば、ケースバイケースでどう対処すればいいのかが見えてくるはずです」。
179頁、「アスクルは、もともと文具メーカーであるプラス株式会社の一事業部としてスタートしました」。